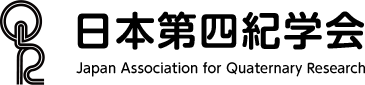過去の大会・総会
過去の大会・総会
| 年 | 開催地 | 大会シンポジウム | 講演要旨集 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 島根大学(8/28~9/1) | 出雲平野と宍道湖の歴史 | no.55 |
| 2024 | 東北大学(8/29~9/2) | 東北の自然災害と第四紀学:最近の研究成果とこれから | no.54 |
| 2023 | 早稲田大学(8/31~9/4) | 都市環境~ウェルビーイングな社会創出のための第四紀研究 | no.53 |
| 2022 | 静岡県地震防災センター(8/26~28) | 伊豆衝突帯とその隣接地域における大規模自然災害 | no.52 |
| 2021 | オンライン-大阪(8/27~29) | 近畿における歴史時代の自然環境 | no.51 |
| 2020 | オンライン(12/26~27) | no.50 | |
| 2020 (総会) |
オンライン(8/28~29) | ||
| 2019 | 千葉科学大学(8/23~26) | 関東平野東部における第四紀研究の最近の成果 | no.49 |
| 2018 | 首都大学東京(8/24~28) | 自然環境と人類の将来予測に向けた第四紀学の最先端:各領域分野の最新動向とその共有・発展をめざして | no.48 |
| 2017 | 福岡大学(8/26~30) | 第四紀研究から防災・減災への多角的なアプローチ | no.47 |
| 2016 | 千葉大学(9/17~20) |
|
no.46 |
| 2015 | 早稲田大学(8/29~30) | 第四紀学から防災教育へのメッセージ | no.45 |
| 2014 | 東京大学(9/5~9) |
|
no.44 |
| 2013 | 弘前大学(8/22~24) | 考古遺跡からみた津軽の人と自然 | no.43 |
| 2012 | 立正大学(8/20~22) | 氷床コア等から得られる第四紀環境情報 | no.42 |
| 2011 | 鳴門教育大学(8/26~28) | 環太平洋の環境文明史 | no.41 |
| 2010 | 東京学芸大学(8/20~22) | 自然史の教育と研究をすすめるために-さまざまな分野からの取り組み | no.40 |
| 2009 | 滋賀県立琵琶湖博物館(8/28~30) | 古環境変動に貢献する湖沼堆積物研究の役割 | no.39 |
| 2008 | 東京大学(8/22~24) | 第四紀後期の気候変動と地球システムの挙動-その原因とメカニズムの解明に向けて- | no.38 |
| 2007 | 神戸大学(8/31~9/2) | 瀬戸内海の変遷-自然・環境・人 | no.37 |
| 2006 | 創立50周年記念大会 首都大学東京(8/4~6) |
|
no.36 |
| 2005 | 島根大学(8/27) | 汽水域における完新世の古環境変動 | no.35 |
| 2004 | 山形大学(8/28) | 活構造と盆地の形成 | no.34 |
| 2003 | 大阪市立自然史博物館(8/29) | 大都市圏の完新統に記録された人と自然の相互作用 | no.33 |
| 2002 | 信州大学(松本)(8/24) | 日本アルプスの形成と自然環境の変遷 | no.32 |
| 2001 | 鹿児島大学(8/2) | 南九州における縄文早期の環境変遷 | no.31 |
| 2000 | 国立歴史民俗博物館(8/25) | 21世紀の年代観-炭素年から暦年へ | no.30 |
| 1999 | 京都大学(8/24) | 活構造と都市地盤・災害─阪神大震災から5年目の発信─ | no.29 |
| 1998 | 神奈川県立生命の星・地球博物館(8/27) | 相模湾周辺の地震・火山とテクトニクス | no.28 |
| 1997 | 北海道大学 | 東アジアから西太平洋へ-陸・海・ヒトのテレコネクション | no.27 |
| 1996 | 東京大学(8/23) | 最終氷期の終焉と縄文文化の成立・展開 | no.26 |
| 1995 | 新潟大学(8/26) | 第四紀学と地震防災 平野の自然と人類史-越後平野を例として- |
no.25 |
| 1994 | 東京都立大学(8/27) | 高精度年代測定と第四紀研究 | no.24 |
| 1993 | 福岡市博物館(8/28) | 東アジアと日本の遺跡をめぐる古環境 | no.23 |
| 1992 | 駒沢大学(9/14) | 災害とその予測-第四紀研究の果たす役割- | no.22 |
| 1991 | 高知大学(8/25) | 黒潮圏の第四紀古環境 | no.21 |
| 1990 | 明治大学(8/19) | テフラ-第四紀研究に果たす多様な役割 | no.20 |
| 1989 | 鳥取県立博物館(8/19) | 日本海沿岸の古地理と古環境-第四紀における陸橋問題を中心にして- | no.19 |
| 1988 | 東北大学教養部(8/21) | 東アジアにおける中・後期更新世の人類と環境 | no.18 |
| 1987 | 神戸市教育研究所(8/27~29) | 陸の古環境復元 | no.17 |
| 1986 | 工業技術院地質調査所(8/20~23) | 日本第四紀研究の諸問題-第四紀地図の作成過程から | no.16 |
| 1985 | 信州大学(8/30~9/2) | 中部日本における後期更新世の諸問題-とくに寒冷気候について- | no.15 |
| 1984 | 学習院大学(7/31~8/1) | 大規模土地改変と第四紀研究 | no.14 |
| 1983 | 静岡市たちばな会館(8/24~26) | 南部フォッサマグナ・フィリピン海プレート北縁のネオテクトニクス | no.13 |
| 1982 | 学習院大学(8/18~21) | 14C年代測定の諸問題,日本考古学と第四紀研究 | |
| 1981 | 富山市科学文化センター(8/27~28) | 最終氷期以降の海水準変動とそれをめぐる諸問題 | |
| 1980 | 福島市市民センター(8/22~24) | 最終氷期における日本の動植物相と自然環境 | |
| 1979 | 沖縄県立博物館(1/20~22) | 琉球列島における後期更新世と完新世の諸問題 | |
| 1978 | 千葉県立文化会館(1/28~30) | 関東平野における第四紀後期の環境変化と文化の発達 | |
| 1977 | 仙台市斎藤報恩会自然史博物館(2/5~6) | 古地磁気と第四紀研究 | |
| 1976 | 大阪市立自然史博物館(1/23~25) | 諸外国および日本における第四紀研究の動向 | |
| 1975 | 金沢大学(2/23~24) | 日本海沿岸の砂丘 | |
| 1974 | 駒沢大学(2/24) | 第四紀における動植物界と環境の変遷―とくにクライマチック・オプチマムを中心として | |
| 1973 | 北海道開拓記念館(1/27~28) | ||
| 1972 | 横浜国立大学(1/29~30) | 自然環境の変遷 | |
| 1971 | 群馬大学(1/30~31) | 南北関東の旧石器の編年に関する諸問題 | |
| 1970 | 大阪府立科学教育センター(1/24~25) | 前期洪積世の諸問題 | |
| 1969 | 東京都立大学(2/1~2) | 洞穴にまつわる第四紀学の諸問題 | |
| 1968 | 静岡大学(2/3~4) | 関東・東海地方のテフロクロノロジー | |
| 1967 | 東京教育大学(2/4~5) | 日本における下部旧石器文化の存否 | |
| 1966 | 京都大学(2/5~6) | 第四紀の生物地理 | |
| 1965 | 東京教育大学(2/7) | ||
| 1964 | 駒沢大学(2/1~2) | アムッド人類および遺跡の研究 | |
| 1963 | 東京(不詳)(2/2~3) | 気候変化 | |
| 1962 | 法政大学(2/3~4) | 日本列島とアジア大陸の接続問題 | |
| 1961 | 明治大学(2/4~5) | 日本におけるヴュルム氷期 | |
| 1960 | 東京大学(2/2) | ||
| 1959 | 明治大学(2/1) | ||
| 1958 | 国立科学博物館(1/26) | ||
| 1957 | 国立科学博物館(1/29) | ||
| 1956 | 創立総会:国立科学博物館(4/29) |