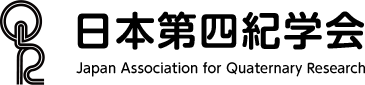会長挨拶
第四紀は258.8万年前に始まり、現在も続く「進行中の地質時代」であり、その期間は今この瞬間も延び続けています。このような特徴をもつ地質時代は他に類を見ません。本学会は、地質学・地理学・古生物学・動物学・植物学・土壌学・人類学・考古学・地球物理学・地球化学・工学・気候学・海洋学など、自然と人間の関わりを研究する多様な分野の専門家が集う、学際的な学会です。その設立(1956年4月29日)の2年後にあたる1958年、ハワイ・マウナロア山で二酸化炭素濃度の観測が開始され、その当時は約315ppmでした。それから70年を経た2025年5月には、430ppmに達しており、この間に115ppmも増加しました。この上昇量は、最終氷期(約2万年前)の190ppmから産業革命前(1750年頃)の280ppmまでの上昇(約90ppm)をも上回ります。この温室効果ガスである二酸化炭素の大量排出により、日本を含む世界各地でかつてない高温現象が観測され、気候変動に伴う様々な災害が発生しています。日本周辺の海域でも温暖化に伴う生態系の変化が生じており、漁業などへの経済的影響が懸念されています。こうした人類による地球環境への深刻な影響を背景に、現在の地質時代を「人新世」として完新世から区分することが国際的に提案されました。正式にはまだ認められていませんが、この考え方は非常に重要な意味を持っています。
このような全球的な気候変動の一方、日本列島は地球規模で見ても地殻変動が活発な「活動縁辺域」に位置しており、2011年の東北地方太平洋沖地震をはじめ、2014年の御嶽山噴火,2016年の熊本地震、2018年の北海道胆振東部地震、そして2024年の能登半島地震など、相次ぐ地震や噴火により甚大な被害が生じています。今後想定される南海トラフ巨大地震への備えも喫緊の課題です。
第四紀学は、こうした自然災害や環境変動の発生メカニズム、それらに伴う生態系の変化、文明との関わりを解明する学問であり、災害のリスク評価や気候変動への対策に欠かせない情報が得られます。こうした情報の重要性は、今後さらに高まっていくことは確実です。
本学会では、年次大会や公開講演会、学会誌『第四紀研究』などを通じて、最先端の研究成果を学会内外に発信しています。また、学会賞・学術賞記念講演会は、どなたでも無料で視聴できるオンライン形式で最新情報を配信しています。
来年に創立70周年を迎えるにあたり、記念事業として記念出版物の刊行を進めており、併せて、国立研究開発法人産業技術総合研究所(つくば市)を会場に、創立70周年記念大会を開催すべく準備を進めております。会員の皆様はもとより、一般の皆様にもご参加いただけるよう企画しております。
日本第四紀学会は、これからも多様な研究分野をつなぐハブとして、第四紀学の発展と社会への貢献を目指して活動を続けてまいります。
どうぞ今後とも一層のご支援とご参加を賜りますようお願い申し上げます。
2025年7月
日本第四紀学会会長
北村 晃寿